新宿のニコンサロンに「忘れられた香港~The Forgotten State」を観に行った。
あの「不肖・宮嶋」、宮嶋茂樹さんの写真展で、きょうが最終日だったのを思い出して出かけたのだった。

〈開催内容〉
100万ドルの夜景を誇る香港、グルメにショッピングに飽くる事なき観光の町、そしてアジアのビジネスの中心となる国際金融都市国家。そんな香港が一昨年以降荒れに荒れた。
1997年7月、香港の主権が英国から中華人民共和国に返還された。その時一番喜んだのは他ならぬ香港市民だった。それ以後50年間は中国政府が国際社会に約束した「香港の高度な自治を認める」いわゆる「一国二制度」は当の中国政府により、わずか22年で崩壊し、香港の実質「一党独裁下」は完成しつつある。
香港でのこれまでの自由な暮らしや、現社会制度を守ろうとする者、そしてそれを破壊し、やがて来る大国の傘の下でしかるべき地位を得ようとする側、その是非を写真家はあえて問わず、ここまでして守るべきものとは一体何か、大国がここまで恐れる思想とは何かを日本人に問いたい。そして写真家はこの双方の戦いを記録すべく、歴史から忘却されることなきよう香港に「通い」つづけた。
しかし、その結果を見ることなく、昨年来ぱったり行けなくなった。中国政府が一方的に定めた、「外国人にまで適用され」「最悪終身刑まで処せられる」新たな法令に我が身の危険を感じたから・・・というより、コロナ禍のせいで。(宮嶋 茂樹)

宮嶋さんは2年前6回香港に通ったという。私の3回の訪問時と重なったこともあったようだ。
シャッターチャンスもアングルも実に効果的ですばらしい。当時の空気が生々しくよみがえってくる。でも、あの高揚はいま、重苦しい沈黙に置き換わってしまった。

香港の思い出話をしていたら、宮嶋さん、「橋田さんの奥さん、3日前に見えられたんですよ」という。「橋田さん」とは、2004年5月にイラクで銃撃され命を落としたジャーナリストの橋田信介さんだ。
宮嶋さんは橋田さんと親しく、毎年、命日にご遺族と追悼する会をしていたという。私はすっかりご無沙汰して失礼していたが、奥さんが、お元気そうで、お孫さんもできたと聞いて安心した。 takase.hatenablog.jp
多くの先輩を失ったことにあらためて気づかされる。
・・・・・・・・
先日、経済評論家・内橋克人さんの訃報を記した。
内橋さんの追悼文を経済学者の金子勝さんが書いていて、興味深く読んだ。
《理論が正しくて、現実が間違っていることはない。
内橋克人の仕事を貫いている精神だと、私は思う。1990年代、バブルが崩壊し、日本経済が行き詰まり出した時、大胆な規制緩和政策が声高に叫ばれた。規制緩和で市場原理を働かせれば、物価が下がって消費者の実質所得が上昇し、新しい産業が生まれるとわかりやすく説明された。この「新自由主義」のドグマはメディアも当然なこととして受け入れていった。
これに対して、内橋は95年に『規制緩和という夢』でアメリカの航空業界の実情を見ながら、安全性をも軽視する規制緩和の問題点を鋭く告発した。そして、規制緩和を主張した経済学者たちに敢然と立ち向かった。その後の格差拡大を含めて、結果は内橋の主張通りになった。当時、私はそれを見ながら、セーフティネット論を組み立てていった。
いつに間にか、人々はできあがったドグマに縛られがちになる。研究者も例外ではない。それを正す役割を果たすのがジャーナリストが突きつける事実の積み重ねである。
しかし、ジャーナリストのこうした作業も、時代の流れに抗うとしばしば孤立することになる。時代に流されるのは簡単だが、それに抗うことはとても難しい。孤立してでもドグマと闘う内橋の姿勢を支えてきたのは、一体何だったのだろうか。直接聞く機会を失ってしまったが、それは、多くの人々が自らの主張を支えてくれるという核心ではなかったのか。(略)
もちろん、内橋の魅力は現状批判の鋭さだけではない。未来を先取りして、代替的なビジョンを打ち出す著作をたくさん書いている。内橋は、2011年の福島第一原発事故を見通すかのように86年に『原発への警鐘』を書いた。そして00年には『浪費なき成長 新しい経済の起点』を書いた。そこで環境問題にいち早く取り組み、「新自由主義」に代えて、北欧のデンマークモデルを紹介し、F(フーズ)、E(エネルギー)、C(ケア)を軸にして地域で雇用を創る新しい経済政策を打ち出した。私も、福島原発事故以後に、農業、自然エネルギー、福祉をベースにした地域分散ネットワーク型経済が、日本経済再生の突破口になると主張するようになった。たしかに内橋は先端の情報通信技術については詳しく展開していないが、私の主張は内橋の先駆的な仕事を踏まえたものである。(以下略)》(朝日新聞9月8日朝刊)
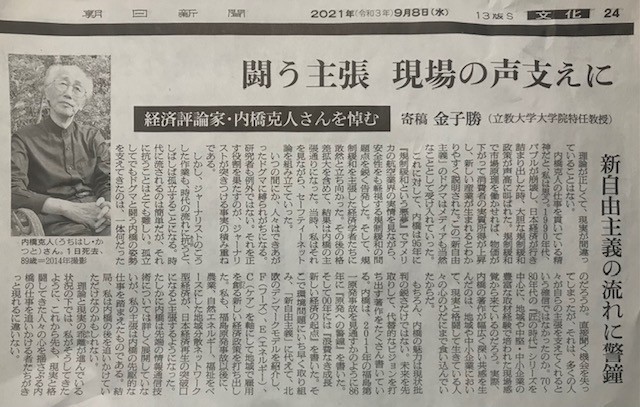
研究者、ジャーナリストのあり方を考えさせられ、また崩壊しつつある日本社会を救い出す道があることに励まされる。