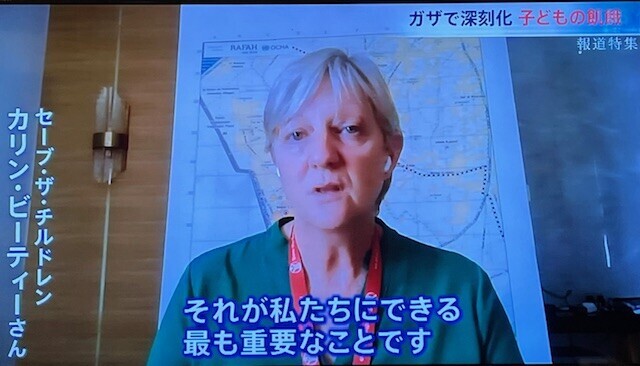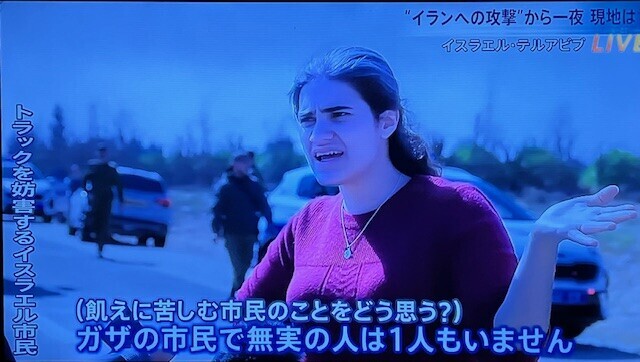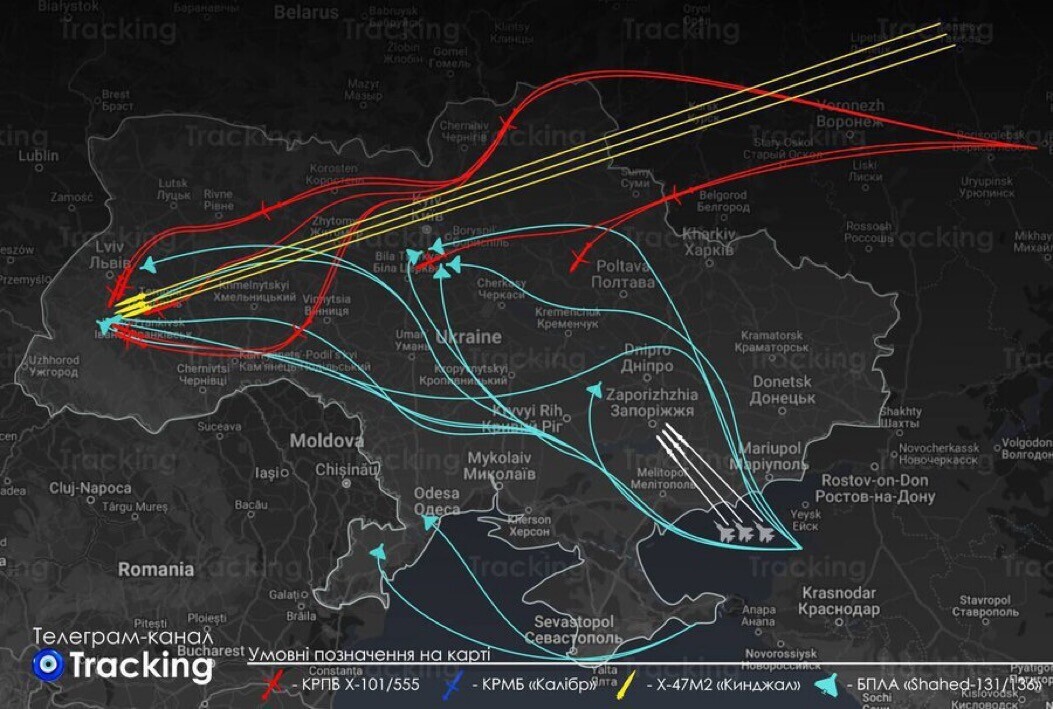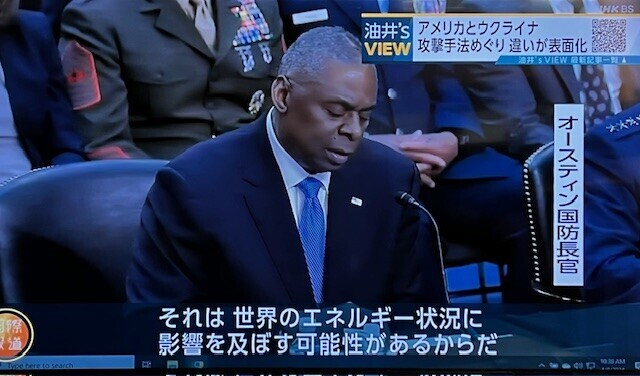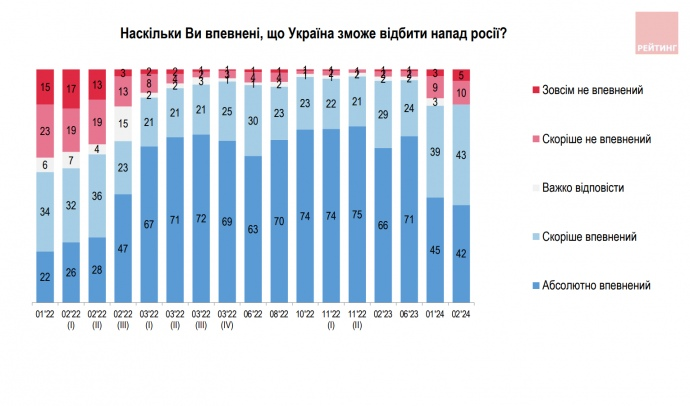イスラエルのAIを使ったガザ爆撃に国際的な非難と憤激が高まっている。
ガザ地区での死者は3万4000人を超えたが、建物の下敷きになっている遺体やカウントされない死者も多いことから、この数字はもっと膨らむと思われる。
これほど多くの人々をイスラエル軍が殺戮するのは、AI(人工知能)を使用することが大きな要因になっているのではないか。その懸念が国際社会で強まっている。
《国連人権理事会に先月、提出されたパレスチナの人権状況に関する報告書では、「イスラエル軍が最初の数か月の軍事作戦で、AIを利用しておびただしい数の建物を標的として特定し、2万5000トンを超える爆発物を使用した」と指摘。
これを受けて、人権理事会では今月始め、「国際法違反の可能性がある軍事的意思決定を支援するAIの使用を非難する」という文言を盛り込んだイスラエルのガザ地区での軍事作戦を非難する決議を可決した。
さらに今月、イスラエルのメディアが、イスラエル軍が空爆の標的を選ぶ上で「ラベンダー」という名前のAIシステムに依存していると報道。過激派の疑いがある人物としてパレスチナ人3万7000人とその自宅がAIシステムに登録され、夜間、寝ている間にAIが自宅を探して空爆。人間が空爆の判断に介在する時間も短く、家族や周辺の一般市民が巻き込まれたなどと伝えた。》
家族や隣人がみな殺しになっても、一人の「過激派」がその中にいればOKということで、膨大な犠牲が出るのは当然だ。そもそもAIがどうやって3万7000人という膨大な数の人々を「過激派の疑いがある人物」と判定するのか。
ハマスという組織は、ガザの行政全般を担っているから、教育や福祉サービスの運営にも関わっている。AIが、ハマスが運営している幼稚園の先生まで「過激派」メンバーとみなす可能性はないのか。

《先週、国連の特別報告者5人が共同声明を発表し、AIによって民間の住宅が空爆の標的とされ、AIがDOMICIDE(ドミサイド)を招いたと非難している。
DOMICIDEとは、意図的かつ組織的に住宅を破壊する行為で、ラテン語の「住宅」と「殺害」の造語。ガザ地区ではすべての住宅の60%から70%が破壊されていて、特別報告者たちはAIによるドミサイド=無差別的な住宅破壊と非難している。》(国際報道24日放送より)

イスラエルはAIの最も邪悪な使い方をしているようだ。
21日の『サンデーモーニング』では、ガザの女性と子どもの惨状が取り上げられた。
「国連女性機関」が16日発表した報告書によると、死亡した1万人以上の女性のうち6千人が母親だった。その結果、1万9千人の子どもが孤児になったとみられる。また、100万人以上の女性と女児が飢餓に直面しており、清潔な水やトイレ、生理用ナプキンを利用できていない。感染症も蔓延している。
《報告書は「清潔な水を利用することは、1日に必要な水分やカロリーの摂取量が多い授乳中の母親や妊娠中の女性にとって特に重要だ」と指摘。女性が尊厳をもって月経を管理するためには、毎月1千万枚の使い捨て生理用ナプキンが必要だとも伝えている》(朝日新聞記事より引用)
国連女性機関の報告書は「ガザでの戦争は女性に対する戦争でもある」と記している。

スタジオで安田菜津紀さんがコメントした。
「これだけの、女性と子どもを含んだ凄惨な事態を、国際社会がなぜ止められずにいるのか。
それに関連しては日本の中にも気になる動きがあって、8月6日に広島では平和式典が行われますよね。そこにウクライナに対する軍事侵攻を続けるロシアは招待されない一方で、イスラエルに対しては変わらず招待を送るということなんですよね。
疑問に思ったのがその理由なんですけれども、「イスラエルの攻撃については世界各国の判断が定まっていないため」というふうに広島市は説明しているんですけれども、じゃ、あと何人のガザの人が殺されたら、あと何人の女性たちが犠牲になったら、あと何人の子どもたちが孤児になったら、広島市は他国の顔色を見ずに主体的な判断ができるのか。
少なくとも「国際平和都市」を名乗るのであれば、そういうダブルスタンダードではなくて人権だったり人道だったり、少なくとも国際法にもとづいた態度を貫くべきだと思います。」
まさに正論。言葉の使い方、話の流れも実に分かりやすく説得力がある。こういうのを「コメント力」というのだな。
日本にいる我々にもやれることがあることを具体的に提示している点でも、すばらしいと思う。遠い国のこととあきらめずに、自分たちにやれることを見つけていこう。